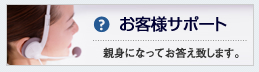弊社は、ビジネスパートナーとして、皆様に役立つ情報、システム等を多角的に提案する、総合コンサルティング企業です。木村泰文税理士事務所(大阪府大阪市)を中心とした『トータルコンサルティング ネットワーク』の中核企業として、ワンストップサービスを提供しています。

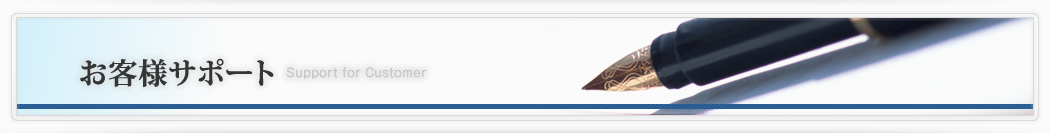
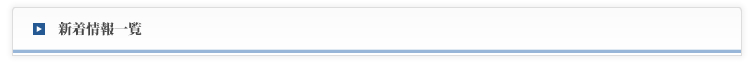
現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。
今回は第71回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。
Q&A成年後見
【質問】
本人は75歳女性。夫はすでに亡くなっており長男と同居して暮らしています。本人の預貯金は同居する長男が管理しています。本人にはほかに長女がおり近隣の町に住んでいます。本人はもの忘れが目立つようになり近所の病院で診てもらったところ認知症と診断されました。長男は本人のために成年後見制度の利用を検討し,自分が後見人等になろうと考えています。長女は長男が⺟の預貯⾦を勝⼿に使っているのではないかと思っており,兄に後見人になってもらうことには不安を感じています。どうすればいいでしょうか。
【回答】
1 本人の財産は兄が事実上管理しており,管理内容の監督を本人ができているかどうか分かりません。成年後見制度を利用すると,後見人等を家庭裁判所が監督するようになり,管理方法や支出内容が透明化されます。
後見人等は家庭裁判所が選任しますので,申⽴⼈の思いどおりになるわけではありません。また,後見等の開始申立てがあった場合,家庭裁判所は本人の身近な親族の意見を求めます。このときに長女が,長男が後見人になることに反対であることを申し出れば,裁判所は親族間で争いがあると判断して長男を後見人等に選任しない可能性もあります。
長女が長男とは別に後見等の開始申立てをすることもできます。長女が自らは後見人等にならないのであれば,家庭裁判所でしかるべき弁護士等の専門職の選任を希望すると申立書に書いておけば,長男が後見人等に選任される可能性は低くなります。仮に長男が後見人等に選任されるとしても,令和4年2月から総合支援型後見監督人の制度運用が開始されていますので,弁護士などの専門職が後見監督人に同時に選任され,原則として9か月の間,長男の事務の指導,相談を行い,今後の事務処理が可能かどうかの監督を行います。長男が後見人として事務処理を適正に行うことができると評価されれば引き続き後見人等としての事務を続けて行うことができます。
2 家庭裁判所が後見人等を監督するといっても,財産管理の状況を常に監督できるわけではなく,事後的に報告の中で不審点を見つけるなどするしかありません。これまでに親族後見人等による使い込みの不正がなかったわけではありません。親族後見人等だけでなく,専門職による不正も残念ながらありました。
後⾒⼈等による不正を防止して,後見制度が安全に信用できるものにするため,親族後見人について,後見制度支援信託(以下「支援信託」といいます),後見制度支援預貯金(以下「支援預貯金」といいます)という制度が導入されています。これは,本人の預貯金が一定額以上(たとえば大阪では1200万円以上)ある場合に,信託銀行(支援信託を利用する場合),信託銀行以外の銀行等(支援預貯金を利用する場合)と契約を結んでお金をまとめて預け入れ,予め契約で決めた生活費が銀行から毎月後見人の管理口座に入金され,それ以外のお金を後見人が引き出す場合は家庭裁判所の許可を必要とする仕組みです。これにより,本人の一定額のお金が固定され,後見人等がお金を自由に引き出すことができなくなり,不正防止になります。ただし,本人の預貯金が複数の銀行に存在している場合は,これらを1箇所の銀行に集めて支援信託,支援預貯金の設定をする必要があり,本人がせっかく自分で決めた財産の管理内容を崩すことになり,本人の意思に反する可能性があります。
支援信託,支援預貯金の利用が可能なのは,本人の財産が基本的に預貯金の場合に限られます。不動産があったり,株式,投資信託などの有価証券などの財産があると,支援信託,支援預貯金を利用することができません。本人が遺言書を作成している場合は,銀行預金の受取人を指定している可能性があり,支援信託,支援預貯金にしてしまうと預金先が変わり,遺言が執行できなくなる可能性がありますので支援信託,支援預貯金の利用はできません。また,この支援信託,支援預貯金は現在のところ,保佐,補助の場合は利用できず,後見の場合に限って利用できることになっています。このように利用できない場面もありますが,本人財産が預貯金のみという事例は多くあり,支援信託,支援預貯金はかなり利用されています。令和2年度で支援信託が累計27,257件,支援預貯金が累計3,522件あり,合計累計額は約1兆140億円に達しています。
※次回の掲載日は、5月31日前後を予定しております。
法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。
お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。