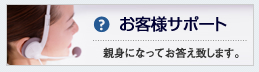弊社は、ビジネスパートナーとして、皆様に役立つ情報、システム等を多角的に提案する、総合コンサルティング企業です。木村泰文税理士事務所(大阪府大阪市)を中心とした『トータルコンサルティング ネットワーク』の中核企業として、ワンストップサービスを提供しています。

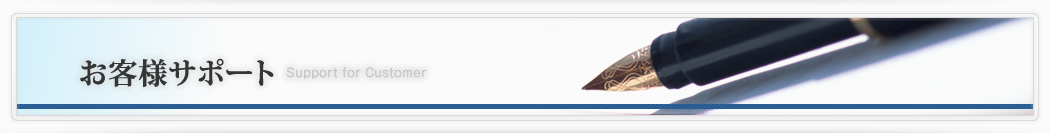
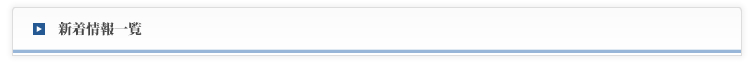
現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。
今回は第92回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。
Q&A成年後見
【質問】
本人は50歳,男性です。総合失調症とアルコール依存症になっており,母名義の自宅で1人暮らしをしています。
本人は22歳で会社に就職しましたが30歳ころに父が亡くなり,同じ時期に統合失調症を発症して退職し,その後は母と自宅で暮らしていました。母は5年前に脳梗塞を発症し,退院後自宅で暮らしていましたが2年前に体調を崩して入院し,退院できないまま昨年死亡しました。
本人には兄がおり,近くの町で暮らしていましたが,7年前に亡くなっており,兄には妻と子ども2人がいます。
母の遺した預貯金と自宅の相続をすることが必要になりましたが,どうすればいいでしょうか。
【回答】
1 母の相続人は,本人と兄の2人のほかに兄弟姉妹がいなければこの2人が相続人です。母の相続については,母と兄のどちらが先に亡くなっているかで相続人の範囲が異なります。母が亡くなり,その後に兄が亡くなると,兄が母を一旦相続し,兄が亡くなると兄の相続人が兄を相続するので,兄の相続人は妻と子ども2人になります。逆に,兄が先に亡くなり,その後に母が亡くなると,母を相続する兄がすでに亡くなっているので,代襲相続といってその直系の者(ここでは子ども2人)が兄に代わって相続人になります。
本件では,母が亡くなる前に兄が亡くなっていますので,兄について代襲相続が生じており,子ども2人が母の相続人になります。従って,本件では本人と兄の子ども2人が母の相続人になります。代襲相続人である子ども2人は兄の相続分(2分の1)を2分の1ずつ相続し,本人の相続分が2分の1,子どもたちの相続分がそれぞれ4分の1になります。
2 亡くなった人の遺産を相続するには,遺産分割を行い,相続手続をすることが必要です。本人に遺産分割の意味とその結果を理解する判断能力があれば,兄の子ども2人との間で遺産分割協議をして預貯金の払戻を行い,協議に従って預貯金を分割し,不動産も協議に従って相続登記や売却などの処分をします。
しかし,本人の判断能力が不十分であれば,遺産分割を行うには成年後見人等を選任してもらい,その支援を受けながら遺産分割を行う必要があります。
兄の子ども2人が未成年であれば,母が未成年後見人として子どものために遺産分割協議を行います。ただ,子どもが2人とも未成年であれば,母は2人の子どもの両方について未成年後見人として遺産分割協議を行うと,利益相反の問題が生じるので,子どものうちどちらか1人だけの未成年後見人として遺産分割協議を行い(遺産分割協議の内容によっては,一方の子どもの利益が他方の子どもに不利益になることが考えられますので,1人の親が2人の子どもの未成年後見人として代理することは双方代理として認められません),もう1人の子どもについては,家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
3 本人に成年後見人等が選任される場合については,
① 本人が判断能力を失っていると考えられる場合は成年後見人を選任してもらい,成年後見人が本人に代わって兄の子ども2人と遺産分割協議を行います(子ども2人に未成年後見人あるいはさらに特別代理人がついていれば,これらの者と遺産分割協議を行います)。
② 本人の判断能力が著しく不十分になっていると考えられる場合は保佐人を選任してもらいます。この場合は,本人が同意すれば,保佐人に遺産分割協議を行う代理権が与えられます。本人が同意しなければ保佐人には遺産分割協議を行う代理権は与えられません。保佐人に遺産分割協議を行う代理権が与えられない場合は,遺産分割協議は本人が子ども2人と行うことになります。保佐人は本人が行う遺産分割協議について同意するかどうかを決めることになります。保佐人の同意なしに遺産分割協議が行われた場合は事後的に取消権を行使することもあります。
③ 本人の判断能力が不十分になっていると考えられる場合は補助人が選任されます。補助人の選任には本人の同意が必要ですし,補助人に遺産分割協議を行う代理権を与えること,あるいは補助人に遺産分割協議についての同意権・取消権を与えることについても本人の同意が必要です。
本人が同意しないと補助そのものが開始しませんし,遺産分割協議についての代理権も同意権・取消権も本人の同意がないと補助人には与えられません。本人の判断能力がまだあるという前提になりますので,遺産分割協議を自分で行うこともできますし,支援を得て行うこともできます。
※次回の掲載日は、4月30日前後を予定しております。
法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。
お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。