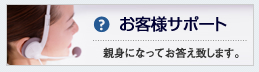弊社は、ビジネスパートナーとして、皆様に役立つ情報、システム等を多角的に提案する、総合コンサルティング企業です。木村泰文税理士事務所(大阪府大阪市)を中心とした『トータルコンサルティング ネットワーク』の中核企業として、ワンストップサービスを提供しています。

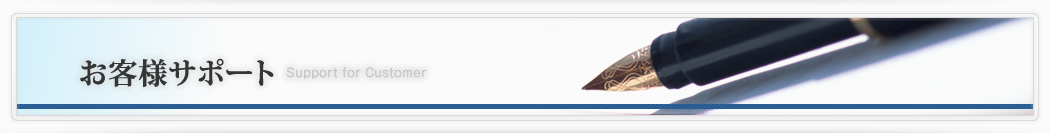
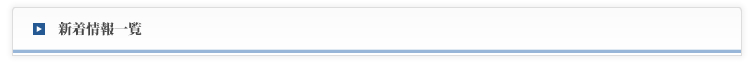
現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。
今回は第96回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。
Q&A成年後見
【質問】
本人は70歳。親族は誰もいません。脳梗塞の後遺症で要介護3の判定を受けており,これまではヘルパーさんに家に来てもらっていましたが,体の状態も悪くなり,このたび要介護4の判定を受けました。本人も1人暮らしがだんだんできにくいと感じるようになっており,特別養護老人ホームに⼊りたいと思うのですが⾝元引受⼈になってくれる⼈がいないと入れてもらえないと聞きました。
どうすればいいでしょうか。
【回答】
⽼⼈ホームに⼊所あるいは病院に⼊院するときに⾝元引受⼈や⾝元保証⼈を求められることがあります。家族が後⾒⼈の場合,家族の⽴場で後⾒⼈が⾝元引受⼈になることはあるかも知れませんが,後見人が⾝元引受⼈や身元保証人になることは,本来は後見人の職務ではありません。
身元引受とか身元保証というのは次のような内容が考えられます。①緊急連絡先,②施設利用料,入院費の支払保証,③本人が施設,病院に対して不法行為をした場合の侵害賠償責任の支払保証,④利用者が退所,退院する場合の居室の明渡,⑤遺体,遺品等の引き取りなどです。契約書に引受人,保証人として署名すると,これらの責任を負担する約束をしたと扱われるおそれがあります。入院費の支払保証や損害賠償の支払保証は,債務の連帯保証人となることを認めるものになる可能性があり,名目は身元引受や身元保証というものであっても,内容は連帯保証責任を負わされることもあるので注意が必要です。
身元引受とか身元保証と言っても,契約書にその内容が書かれず,単に身元引受とか身元保証と書いてあるだけでは,裁判になればその解釈をめぐって紛争になる可能性があります。契約書に署名する時点で,身元引受あるいは身元保証の具体的内容を明記してもらうようにするのが望ましいといえます。そう言ったところで受けてもらえないかも知れませんが,そうしなければお互いに後で生ずるトラブルを覚悟する必要があります。
身元引受人や身元保証人がいない場合については,身元引受や身元保証を引き受けることをうたい文句にする民間の一般社団法人やNPO法人があります。これらの法人は,身元引受や身元保証だけでなく,日常の金銭管理,役所関係の手続やケアプランの打合せなどの生活サポート,葬儀や納骨手配,任意後見など生活上の不安を包み込むような広範囲の業務を行うとしています。老人ホームと提携している法人もあります。預託金としてまとまった金額の先払いを求めるところもあり,また,支払う費用が相当高額になることもあります。利用する場合は,身元引受や身元保証の必要性にだけ目を奪われず,本当に必要なサービスなのかよく考えてからにすることが大切です。
なお,厚生労働省は,令和6年6月に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を公表し,サービス提供に当たっての基本的な考え方を示しています。
また,厚生労働省は,福祉施設について,「法令上は身元保証人等を求める規定はなく、入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない」との見解を示しています(「市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポートの事業に関する相談への対応について」厚労省平成30年8月30日老高発0830第1号/老振発0830第2号)。病院については,身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否することは「医師法19条1項に抵触する」という通知も出しています(「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて」厚労省平成30年4月2日医政局医事課長通知医政医発0427第2号)。
※次回の掲載日は、10月31日前後を予定しております。
法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。
お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。