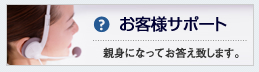弊社は、ビジネスパートナーとして、皆様に役立つ情報、システム等を多角的に提案する、総合コンサルティング企業です。木村泰文税理士事務所(大阪府大阪市)を中心とした『トータルコンサルティング ネットワーク』の中核企業として、ワンストップサービスを提供しています。

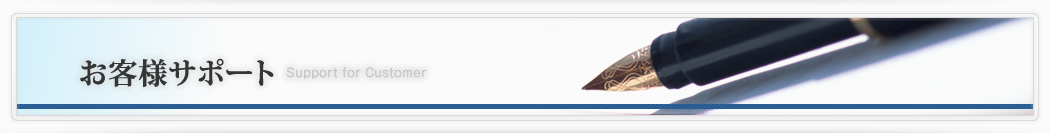
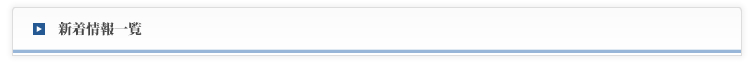
現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。
今回は第97回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。
意思決定支援
1 意思決定支援について
認知症や知的障がいがあるためにものごとを判断するのに困難を抱えている人は,「何も決められない人」と思われやすく,食べ物を決めるような日常的な場面からどこで暮らすかなど重要なことを決める場面に至るまで,支援者など第三者が本人を誘導,説得して自分で決めたようにしたり,本人に全く聞かずに第三者が決めてしまうことがあります。このような支援のあり方に対しては,「私たち抜きに私たちのことを決めないで」を合い言葉に,個人の尊厳に基づき,決めるのは本人であるとして,本人中心に考える意思決定支援の考えが示されています。
障害者基本法や認知症基本法などには,すでに「意思決定の支援」という文言が入れられていますが,これだけでは意思決定支援が何をすることか分からないので,意思決定支援を行う際の指針(ガイドライン)が障がい福祉,認知症の人,成年後見の分野を対象に公表されています。
2 意思決定支援とはどうすること
意思決定支援という漢字だけ見ても抽象的で分かりにくいので,もう少し分かりやすく考えると,意思決定というのは「決める」こと,「選ぶ」ことであり,意思決定支援は決める必要のある「課題」について本人が決めることができるよう支援することです。意思決定支援はどのようにするかというと,「あなたはどうしたいのですか」と聞いて本人が表明した意思を尊重して支援していくことです。「あなたはこうするのがいいです」と,支援者が本人にしてほしいと思うことを本人に押しつけたり誘導することは意思決定支援とはいえません。本人が言葉で意思表明するのに困難があるのであれば,「この人はどうしたいのだろう」と考えながら,本人の表情や普段の行動から本人の思いや好みを読み取り,読み取った意思を支援していくことになります。
3 意思決定支援の方法,プロセス
意思決定支援には,意思形成支援,意思表明支援があると言われています。形成とか表明というのは抽象的で分かりにくいですが,要するに本人が自分の考えを決め,決めたことを外部に表明する支援をすることであり,難しいことが言われているのではありません。意思形成,意思表明の支援が適切に行われるには支援者が留意する必要のあることがあります。本人に分かりやすい言葉でゆっくり話すとか,誘導はできる限り避けるとか,本人に決断を迫って焦らせないとか,支援者の考えを押しつけないなど留意することがいくつかあります。本人の意思が表明されれば,本人にできることは本人にしてもらいながら意思の実現支援をします。
4 意思決定支援の基本原則
意思決定支援には基本原則があります。第1原則は,どんな人も意思決定をする能力があると推定するということです。意思表明できないから意思決定できないと考えるのではなく,本人には意思決定できる能力があると考え,本人が意思表明するようできる限りの支援を行い,言葉で表明ができないときは,本人の行動や表情などから本人の意思を読み取るなどの努力をするということです。第2原則は,本人が意思決定をするために実行可能なあらゆる支援をするということです。本人が意思決定するために実行可能なあらゆる支援をした後でなければ,本人には意思決定能力がないと判断してはいけないということが第2件原則の意味です。第3原則は,本人が不合理にみえる判断をしたとしても意思決定できないとみなさないということです。支援者からみると不合理にみえることを本人が決めたとしても,それも本人の判断として尊重し,本人には意思決定能力がないとは考えないということです。
5 意思決定支援の限界
このような意思決定支援の基本原則については,本人の言うことは全て聞かなければならないのか,本人にどんな不利益な意思決定であっても実現支援しなければならないのかという疑問が示されるかもしれません。これについては,意思決定の内容が本人にとって見過ごすことのできない重大な影響を生ずる場合には実現に協力しない,あるいは第三者が本人に代わって決定することを検討することが考えられています。意思決定支援といっても絶対的なものではなく,限界はあると考えられます。
6 意思決定支援のマインド,意識改革
成年後見制度の理念として自己決定の尊重が言われていますが,現実には本人の意思を中心に考えるというよりも本人保護の考えから,保護者的に「あなたはこうした方がいい,ああした方がいい」と言って本人を誘導して決めさせたり,本人に代わって決めることが多く行われています。意思決定支援は,このような考え方,意識に変革を求めるものです。意思決定支援は,決定するのは本人であり,本人の希望,好み,価値観を尊重して支援すべきであり,課題についての結論を考えるのは支援者ではなく本人が自分で選択すると考えて行う支援です。
意思決定支援は意識改革(パラダイム転換)の必要があると言われています。それは保護者的な支援の考え方から本人中心の考え方に支援の考え方を変えるということです。これまでの保護者的な支援の考え方からすると,180度の意識転換が求められているといえます。丁度,毎日見ている日の出日の入を,太陽が地球の周りを回っていると考える天動説から,そうではなく,地球自身が自転しながら太陽の周りを回っていると考える地動説へ発想を切り替えるのと同じくらい大転換が必要といえます。
※次回の掲載日は、11月30日前後を予定しております。
法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。
お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。